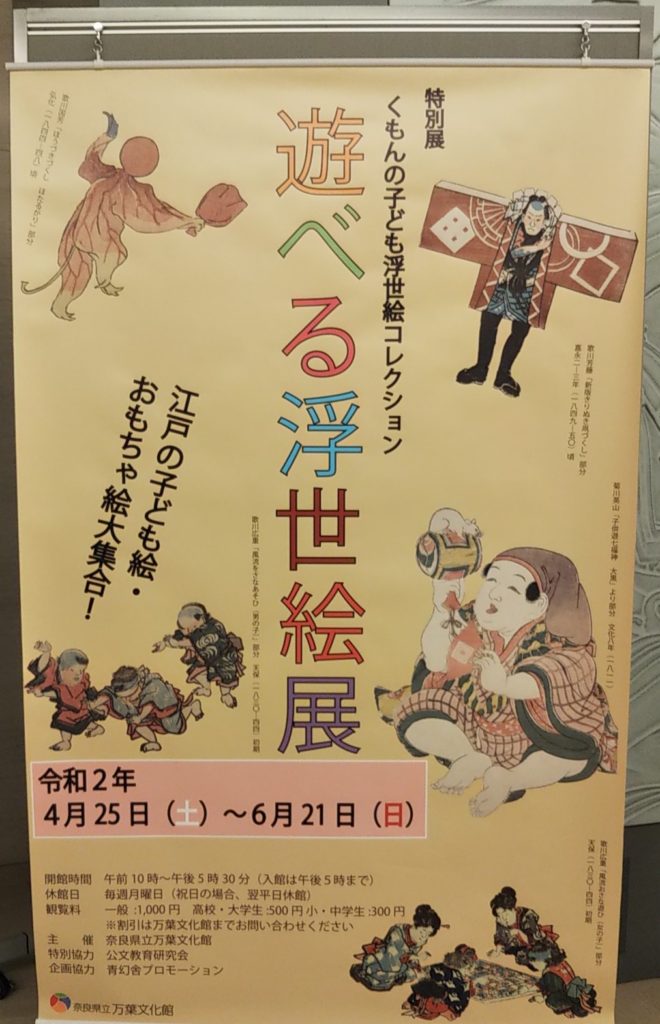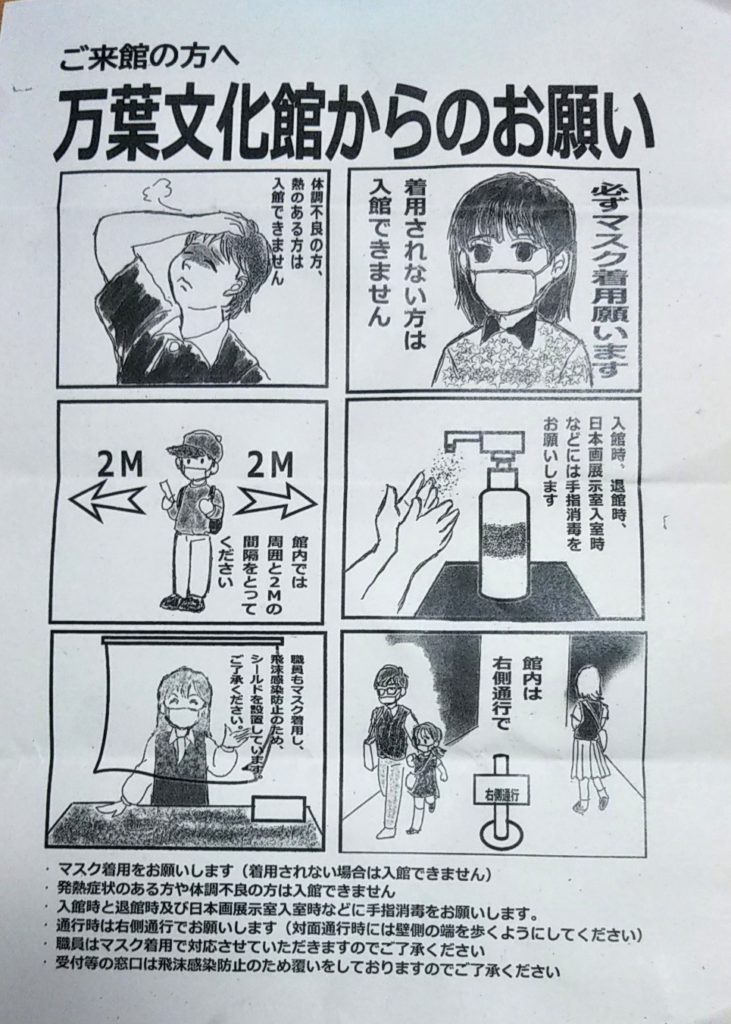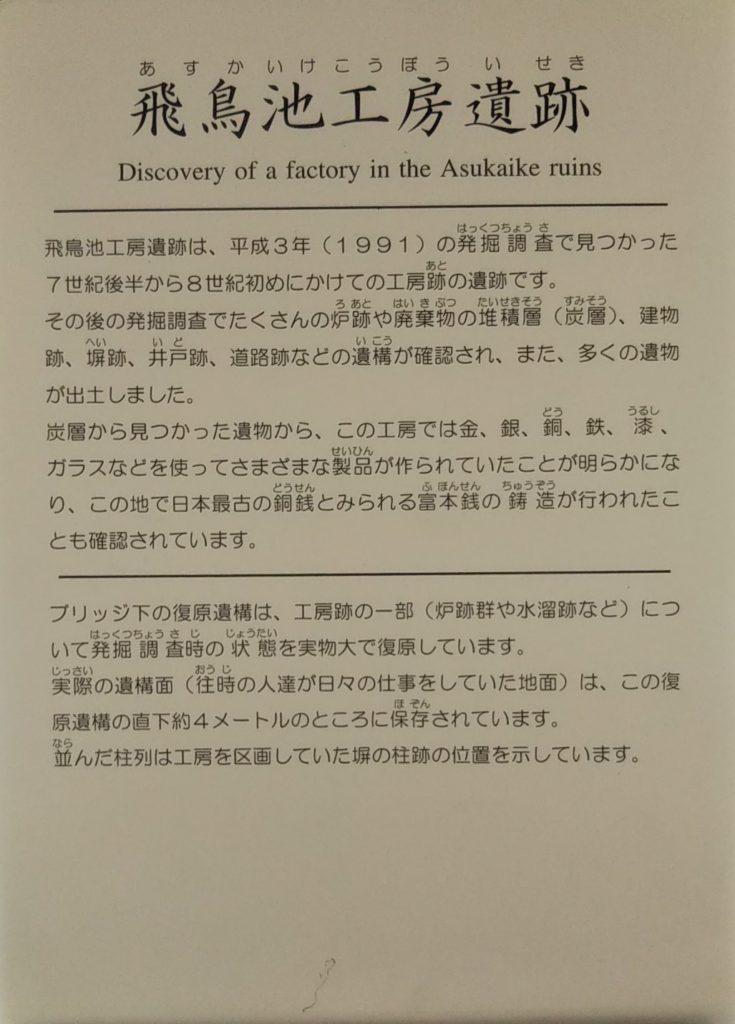タイトルの通り、今年行きたい展覧会を現時点で発表されているもので 関西を中心に調べて並べてみました。あれこれ考えるだけでワクワクしてきますね。下記のリストは自分用の備忘録のようなものです。よかったら参考にどうぞ。
後半は「行けないけど興味のある展覧会」をリスト化しています。やはり東京方面、おもしろそうな展示が目白押しですね!どこでもドアがあれば行けるのに!!
展覧会リスト (会期始まりの早い順)
※【会期】【開催館】「展覧会タイトル」(巡回があればその開催都市)の順で記載しています
〜1/22 奈良国立博物館「春日大社 若宮国宝展―祈りの王朝文化―」
~2/5 京都国立博物館 名品ギャラリー「十二天屏風の世界」
~2/5 京都国立博物館 名品ギャラリー「京を描く―洛中洛外図屏風―」
~2/12 京都市京セラ美術館「アンディ・ウォーホル・キョウト/ANDY WARHOL KYOTO」
~2/12 佐川美術館「特別企画展 あけてみよう かがくのとびら展」
〜3/13 春日大社国宝殿「杉本博司―春日神霊の御生御蓋山そして江之浦」
1/21〜4/2 大阪中之島美術館「大阪の日本画」(巡回展:東京)
2/7~3/5 京都国立博物館 名品ギャラリー「京都の狩野派―狩野山楽―」
2/17~3/26 美術館「えき」KYOTO「ミュシャ展 マルチ・アーティストの先駆者」
2/3~3/28 パラミタミュージアム「川瀬巴水―旅と郷愁の風景―」
3/18〜5/28 大阪市立自然史博物館「特別展 毒」(巡回展:東京)
3/25〜5/21 京都国立博物館「親鸞 生涯と名宝」
4/16〜6/11 京都市京セラ美術館「マリー・ローランサンとモード」(巡回展:東京、名古屋)
前期4/22〜5/21後期5/23〜6/18 あべのハルカス美術館「幕末土佐の天才絵師 絵金」
4/22〜6/25 京都文化博物館「大名茶人 織田有楽斎展」
6/10〜7/17 泉屋博古館「歌と物語の絵ー雅やかなやまと絵の世界」
6/27〜9/24 京都市京セラ美術館「ルーブル美術館展 愛を描く」(巡回展:東京)
7/8〜9/3 奈良国立博物館「聖地 南山城―奈良と京都を結ぶ祈りの至宝―」
1期9/10〜11/12・2期11/19〜24/1/28 相国寺承天閣美術館「若冲と応挙」
10/7〜12/3 大阪中之島美術館「生誕270年 長沢芦雪」
10/7〜12/3 京都国立博物館「東福寺」(巡回展:東京)
10/26〜24/1/14 大阪中之島美術館「テート美術館展 光―ターナー、印象派から現代へ」(巡回展:東京)
★注目しているのは、大阪中之島美術館「大阪の日本画」展、あべのハルカス美術館「幕末土佐の天才絵師 絵金」展、大阪中之島美術館「生誕270年 長沢芦雪」展。
大阪中之島美術館の比率が高いですが、昨年オープンしてからまだ訪れたことがありません。そういう意味でも興味津々です。
行けないけど興味のある展覧会 (会期始まりの早い順)
〜1/29 神戸ファッション美術館「祝祭の景色 世界の結婚式」
〜1/31 丸紅ギャラリー「ボッティチェリ特別展《美しきシモネッタ》」
〜3/22 岐阜現代美術館「篠田桃紅 屏風」
〜3/26 出光美術館「江戸絵画の華」
〜4/2 日本民藝館「生誕100年 柚木沙弥郎展」
〜5/28 東京都現代美術館「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」
〜6/4 岡田美術館「若冲と一村―時を越えてつながる―」
3/11〜5/7 府中市美術館「春の江戸絵画まつり 江戸絵画お絵かき教室」
3/18〜4/16 板橋区立美術館「椿椿山展 軽妙淡麗な色彩と筆あと」
3/18〜5/21 富山県美術館「生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」(巡回:青森、東京)
3/21〜6/11 国立工芸館「ポケモン×工芸展」
4/15〜5/28 徳川美術館「大蒔絵展ー漆と金の千年物語」
4/27〜8/20 東京都美術館「マティス展 Henri Matisse : The Path to Color」
6/3〜7/23 泉屋博古館東京「木島櫻谷―山水夢中」
7/15〜8/20 根津美術館「物語る絵画」
9/20〜12/11 国立新美術館「イブ・サンローラン展」
10/7〜12/17 パナソニック汐留美術館「コスチュームジュエリー 美の変革者たち シャネル、スキャパレッリ、ディオール 小瀧千佐子コレクションより」
10/11〜12/3 東京国立博物館「やまと絵―受け継がれる王朝の美―」
12/9〜24/3/3 アーティゾン美術館「マリー・ローランサン ―時代を写す眼」
★東京都現代美術館「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展は既に予約がいっぱいで人気のようですね!自分自身は着飾るのが下手ですが昔から服飾には興味があります。「イブ・サンローラン展」もありますし、大手メゾンの展覧会は夢と憧れが詰まっています。
他にも面白そうな展覧会がたくさんありますが、東京遠征はできないので、他の方のレポなど見て雰囲気だけでも楽しみたいと思います。
(読んでいただきありがとうございます。誤植などありましたらぜひお知らせください)